|
味の正四面体
味覚の働き
ありきたりでおもしろみのないことを「無味乾燥」とか「味気ない」といった言葉で表現しますよね。文字どおり食べ物に味がなかったら、食欲もわいてこないでしょう。この食べ物の味を感じとる感覚を味覚といい、おもに舌の表現に存在する味蕾(みらい)で知覚します。味覚の最も大切な役目は食欲を増進させることです。
私たちが感じる味は「あまい」「からい」「すっぱい」「にがい」の四つの基本的な味の、強弱の組み合わせによって生じていると考えられています。つまり四つの味を頂点とする正四面体で表現することができます。
|
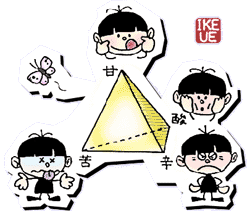
|
|
「あまい」とは、砂糖・ブドウ糖などの糖類によって生じる味で、人間にかぎらず、あらゆる生き物にとって、非常に好まれます。体に大切なエネルギー源の炭水化物を摂取するための味と考えられています。「からい」とは食塩に代表されるように、体に必要なミネラルを検出するための味と考えられています。
「すっぱい」とは酸の味のことです。レモンなどのおいしい酸味もありますが、腐敗物は酸を含みますので酸っぱい味がします。そして、「にがい」は毒物を判断する味と考えられています。毒物の多くは苦い味をしています。人間にとって有害なもの・危険なものは、「にがい」や「すっぱい」などのいやな味がするので、思わず吐き出したりして、飲み込まないようになっているのです。
このように、味覚には、食欲の増進だけでなく、人間にとって有害なものを誤って食べないように、体の安全を守る役目もあります。
最近、脳挫傷(のうざしょう)を受けて植物状態になった患者さんに味覚刺激を与えると、脳が活性化されて全身状態がかなり改善されたということが発表されて、注目を集めています。味覚は、身体が不自由になった方にも、最後まで残る心地よい感覚で、脳の活性化にも大変役立っています。今後、このような研究が進歩して、老人性痴呆(ちほう)などの治療に生かされるのではないかと期待しているところです。 |
|
|
|
|
|