|
歯科心身症・1
病は気から、大切な心の治療
病気という英語diseaseは、dis(〜でない)とease(安楽な、くつろいだ)の合成語です。ですから治療とは、単に病気(安楽でないこと)が解除されるだけでなく、患者さんの心から安らかになるようにすることが本来の姿であるべきでしょう。「病気を治す」のではなく「病人を治す」ことの必要性は、患者さんの側からの願いであることはいうまでもなく、医療を行う側の務めでもあります。ところが現代医学では、ややもすると各種の検査によって病気を発見し、その治療に力を注いで、病気によって不適応になった患者さん自信の心は見過ごされる傾向があります。
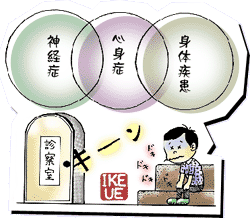 |
|
とくに歯科医療では、正確な入れ歯を作ったり微細な歯の治療をしたりなど、精度を要求される仕事が中心であるため、形や機能の回復が科学的にできればそれで事足れりとされがちでした。患者さん自信がなじんでそれらを使いこなするかどうかについては、あまり注意を払わなかったきらいがありました。
ところが、口膣(こうくう)は物を噛んだり、飲み込んだり、話したり、呼吸をしたりと複雑多彩な働きをもっているので、わずかな不調和でも傷みや損傷として大きく感じられるものです。また歯の治療というと、ほとんどの人が傷みや騒音などを連想し、不安や緊張を伴うようです。だからこれからの歯科治療は、患者さんの精神なケアにも力を注がなければなりません。
では最近よくいわれる「心身症」とはどのような病気でしょうか。心身症とは身体の症状を主としていますが、その診断や治療に、心理的な因子についての配慮がとくに重要な意味をもつ病気のことです。また身体的な原因で起こった病気でも、その経過に心理的な因子が関係している場合や、一般に神経症とされる病気でも身体の症状を主とする場合は広い意味で心身症として取り扱っています。たとえば、胃潰瘍や自律神経失調症などがよく知られています。
心身症はストレスとおおいに関係があります。現代社会におけるストレスが原因で、歯科の領域でもこの心身症といわれる病気が最近増えてきました。 |
|
|
|
|
|